- 物理のエッセンスとはどんな問題集なのか
- 物理のエッセンスをやるべき人はこんな人
- 物理のエッセンスの物理を苦手科目から得意科目にする使い方
- 物理のエッセンスの次にやるべき問題集
大学受験物理の定番の参考書である「物理のエッセンス」。
うまく使いこなすことで東大や医学部の入試問題を解く上で必要な物理の基本的な考え方を身につけることができます。
私はもともと物理は苦手科目でしたが、「物理のエッセンス」から物理の受験勉強を開始し、結果的には東大模試で偏差値76.9を取れるまで物理の成績を伸ばすことができました。
今回はこの問題集の効果的な使い方を紹介したいと思います。
物理のエッセンスとは
「物理のエッセンス」は高校物理の各分野の基礎を例題や練習問題を交えながら、わかりやすくかつ簡潔に解説してる講義系参考書です。
力学・波動編と熱・電磁気・原子編の2冊にわかれています。
「物理のエッセンス」は以下のような構成になっています。
- 物理現象と公式の解説
- 問題の解き方の解説
- 例題
- 例題の解説
- 誤答例
- 練習問題
各章においてまず物理現象とその概念や公式の説明があります。
図が多用されており、直感的に理解しやすいのが特徴です。
次に問題の解法の定石とその定石を使う例題とその解説がまとめられています。
例題の解説には多くの人が間違いやすい誤答例が紹介されていることもあり、参考になります。
そして、各章の章末に練習問題が何題かあり、その解答解説は別冊にまとめられているという形式になっています。
それぞれの分野の練習問題の数は以下の表の通りです。
| 分野 | 練習問題数 |
| 力学 | 114問 |
| 波動 | 70問 |
| 熱 | 33問 |
| 電磁気 | 95問 |
| 原子 | 40問 |
合計352問の練習問題が掲載されています。
物理のエッセンスの内容レベル的には教科書レベルですが、教科書の何倍もわかりやすく、物理現象をより正確に捉えることができるようになります。
物理は公式を覚えてなんとなく公式を問題に当てはめるというような勉強法で勉強していると必ず成績が伸び悩みます。
その方法だと医学部、東大の入試問題を解けるレベルに到達できないことがほとんどです。
医学部、東大入試を突破する上で物理は”物理現象の理解”が一番大切です。
自分が解いた問題の解法を他人に説明できるレベルの理解が必要です。
物理のエッセンスの素晴らしいところは物理現象を理解できるだけでなく、入試問題へのアプローチの仕方も同時に学べるところで、このアプローチ方法は問題が難しくなっていったとしても通用する方法となっています。
物理のエッセンスをやるべき人
これから大学受験に向けて本格的に物理の勉強をはじめようと思っている東大や医学部といった難関大志望者におすすめです。
これまで学校で物理の勉強を定期試験前しかやってなかったという人が大学受験対策に一番最初に手をつける参考書として最適です。
また、物理の勉強を少しやっているが、物理現象をよく理解しないままなんとなく公式を当てはめて解いてしまっているという人にもおすすめです。
私は「物理のエッセンス」に出会う前は定期試験前に学校で配られていた問題集に取り組んでいました。
その問題集の問題は解けるものの模試になると手も足も出ないという状況で、物理は苦手科目でした。
しかし、「物理のエッセンス」を始めてからは成績が一気に伸びました。
「物理のエッセンス」よりレベルの高い参考書に取り組んでいるが、思うように結果が出ないという人も思い切って「物理のエッセンス」から勉強し直すのはありだと思います。
物理の基本的なことは理解できており、入試レベルの問題に取り組むことができている方は物理のエッセンスをやる必要はないです。
物理のエッセンスの使い方
基本的な進め方としては参考書の構成通りに、講義部分の解説を読む→例題を解く→練習問題を解くの順に進めていきます。
物理のエッセンスはボリュームの多い参考書ではないので1周するのにそれほど時間はかかりませんが、その分何周かして考え方を定着させていくのが良いです。
この問題集に取り組むにあたって最終目標は講義部分を全て理解し練習問題も全て解けるようなった状態です。
実際に私がこの状態になるまでにどのように「物理のエッセンス」に取り組んだかを紹介します。
まずは講義部分を全て順に読んでいきます。「Q&A」や「知っておくとトク」といった追加部分も読み飛ばすことがないようにします。
講義部分を読み進めていくと例題が出てきます。講義部分を見ながらでもいいので、例題に取り組みます。
解けた場合も必ず解説を読みます。
続いて練習問題に取り組みます。例題の時と同様に講義部分を見ながらでも問題ありません。
step1~3では問題集の講義部分や例題と練習問題の解説を理解することに注力してください。
なぜなら、1周目にどれだけしっかり解説を理解できるかで、2周目以降の演習効率は大幅に変わるからです。
1周目で解説の理解が曖昧のまま2周目に入ると、再び解説を読んで理解することに時間をかけることになってしまいます。
したがって、1周目の時点でわからない部分に関しては調べたり人に聞いたりして必ずその場で解決します。
わからないことが解決したら2周目以降に再び調べたり人に聞いたりすることを繰り返さないように自分なりの解説を問題集に書き加えておきます。
1周目でしっかりと理解することができていれば、2周目以降の演習のスピードがあがり、学習効率が上がります。
決してわからないところを放置したまま、先に進むことがないようにしてください。
理解をより深めるためにstep1から3までで行ったことをもう一度繰り返します。
普通の人は一回読んだくらいで、完全に理解することはできていません。
1周目に気づいていなかった部分に気づくこともあるでしょう。
今回は講義部分を一切見ることなく練習問題をもう1周します。
この時に間違えた問題にはマークを入れておきます。
4周目は3周目に解けなかった問題のみ取り組みます。
5周目は4周目に解けなかった問題のみ取り組みます。
これを解けない問題がなくなるまで、繰り返します。もちろん講義部分は一切見ずにこれを行います。
「物理のエッセンス」の練習問題を全て解けるようになった時、高校物理の基本的な考え方は習得したと言えるでしょう。
この問題集だけで全統模試偏差値60程度までは到達可能です。
この勉強法で私の場合、力学・波動編は22時間、熱・電磁気・原子編は20時間かかりました。
物理のエッセンスの次にやるべき問題集
東大、京大や医学部などの難関大を志望している方は「物理のエッセンス」だけでは合格できません。
「物理のエッセンス」では物理の基本的な考え方や問題へのアプローチ方法を習得できますが、入試レベルの問題の演習が足りまないからです。
「物理のエッセンス」の次にやる問題集として「名問の森」がおすすめです。
「名問の森」は「物理のエッセンス」と著者が同じ問題集です。
入試問題のパターンが網羅されており、しっかり演習量を積むことができます。
「物理のエッセンス」をしっかりやり込めた人は「名問の森」を難なく取り組むことができます。
しかし、「名問の森」が少し難しく感じる人は「良問の風」を間に挟んでも良いと思います。
「良問の風」も「物理のエッセンス」と「名問の森」と著者が同じ問題集です。「名問の森」より易しい問題が掲載されています。
「名問の森」について勉強法等詳しくは下記の記事をご覧ください。
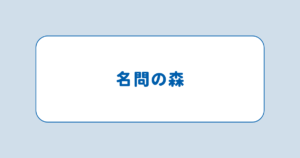
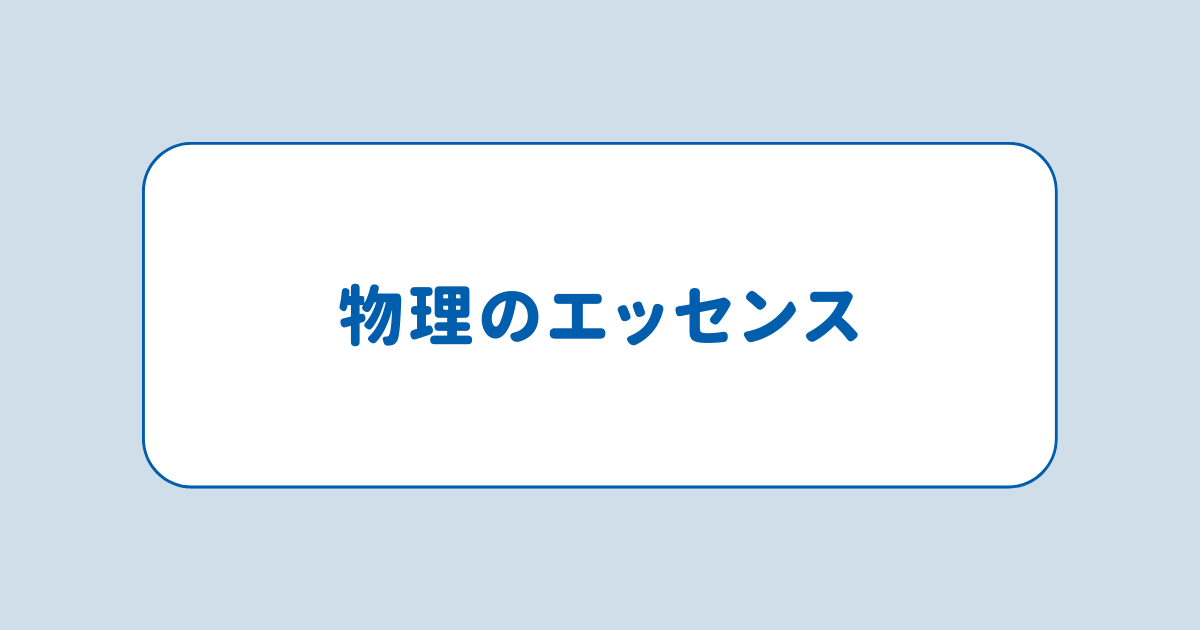
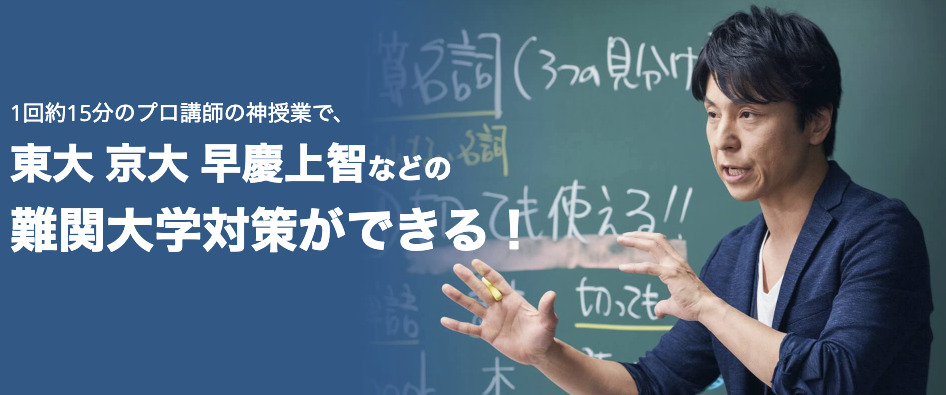
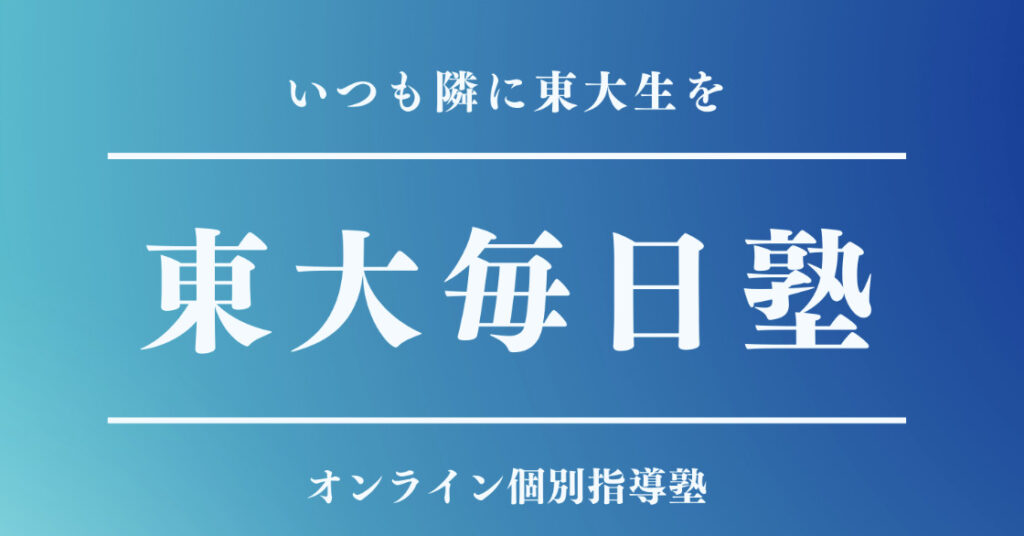
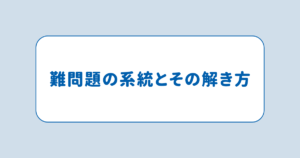

コメント