- 化学の新演習とはどんな問題集なのか
- 化学の新演習をやるべき人はこんな人
- 化学の新演習で難関医学部や東大で高得点を取るための使い方
- 化学の新演習の次にやるべき問題集
東大や難関医学部に合格する人の多くが使っている問題集である「化学の新演習」。
化学が得意な人がより高得点を狙う場合に非常に役に立つ問題集です。
私はこの問題集をやりこむことによって東大の化学においても本番で51/60という高得点を取ることができるまで化学の成績を上げることができました。
しかし、「化学の新演習」に掲載されている問題はハイレベルなものが多いので、適切なレベルの人が適切な使い方をしないと時間の無駄になってしまう可能性もあります。
今回はそんな私の化学の成績向上にかなり貢献した「化学の新演習」についてどんな人がどのように使えばいいのか解説したいと思います。
化学の新演習とは
「化学の新演習」は大学入試問題から、今後も類似の問題が多く出題されると思われる典型問題や比較的長文で実力強化に役立つと思われる問題が掲載されている問題集です。
問題の難易度は高い方で、難関大対策に特化した問題集といえます。
「化学の新演習」は理論、無機、有機の全分野の問題が網羅的に1冊にまとめられており、問題の難易度は三段階に分けられて、問題の横に星の数で表されています。
「化学重要問題集」と難易度が被っている問題も多少ありますが、ほとんどの問題はより発展的な内容になっています。
「化学の新演習」に掲載されている問題の問題数を単元ごとにまとめて表にしました。
| 単元 | 問題数 |
| 物質の構造 | 36 |
| 物質の状態 | 42 |
| 物質の変化 | 88 |
| 無機物質の性質 | 47 |
| 有機物質の性質 | 72 |
| 高分子化合物 | 46 |
全部で331問あります。
この問題集を完成させた場合、どんな大学の化学の問題においても高得点を取ることができるようになります。
東大理科3類受験生だったとしても、合格点を取ることは十分にできます。
化学の新演習をやるべき人
「化学の新演習」は東大化学で高得点を狙っている人や慶應大学医学部や京大医学部、東大理科3類など難関医学部を目指している人にはおすすめです。
東大志望や医学部志望であったとしても、上記に当てはまらない人にとっては優先度の低い問題集です。
また、東大化学で高得点を狙っている人や難関医学部を目指している人でも、化学の入試標準問題を難なく解けるレベルにない人は手を出さない方がいいです。
「化学重要問題集」の問題が全て解けるようになった人が次に「化学の新演習」に取り組むとスムーズに学習を進めることができます。
まだ、「化学重要問題集」を完成させていないと言う人はまず先に「化学重要問題集」から始めてください。
詳しくは下記の記事をご覧ください。

化学の新演習の使い方
基本的な学習の進め方は問題集の前から問題を解いていき、全ての問題が解けるようになるまで繰り返すという方法がおすすめです。
この問題集に取り組むにあたって最終目標は全ての問題において他人に説明できるくらい理解し、完全解答できるような状態です。
実際に東大や難関医学部で出題される発展的な内容の問題も「化学の新演習」に載っている問題の類題であることが多いです。
また、超難関大学で出題される真新しい問題に対する応用力も身につけることができます。
実際に私がこの状態になるまでにどのように「化学の新演習」に取り組んだかを紹介します。
まずは問題集の前から問題を解き進めていきます。
「重要問題集」を完成させていれば、1周目であったとしても解ける問題は少なくないと思います。
わからない問題があったとしてもすぐに解説を見るのではなく、落ち着いて考えてみてください。
発展的な化学の問題は問題文が長く、情報を整理することが難しいです。
解法の方針がすぐ立たなかったとしても、図を書くなどして手を動かしてみてください。
それでもわからない場合は解説を読みます。解説を読む時も実際に自分の手で計算しながらだとより良いです。
1周目では解説を理解することを最優先してください。
「化学重要問題集」を完成させている人であれば、一人で解説を読んで十分理解できると思います。
ここでわからない部分に関しては調べたり人に聞いたりして必ずその場で解決してください。
わからないことが解決したら2周目以降に再び調べたり人に聞いたりすることを繰り返さないように自分なりの解説を問題集に書き加えておきます。
1周目でしっかりと理解することができていれば、2周目以降の演習のスピードがあがり、学習効率が上がります。
決してわからないところを放置したまま、先に進むことがないようにしてください。
1周目にできた問題を含めて全問題さらに2周目、3周目を行います。
難関大で出題される発展的な化学の問題のほとんどは「化学の新演習」に掲載されている問題のどれかの類題であるため、全問題3周することで問題のパターンを徹底的に頭の中に詰め込みます。
3周もすれば完全に解ける問題もいくつかあるでしょう。
4周目は3周目に解けなかった問題のみ取り組みます。
5周目は4周目に解けなかった問題のみ取り組みます。
これを解けない問題がなくなるまで、繰り返します。
注意点としてやり方は合っていたが、計算ミスをしまったというような場合でも必ずもう1度解き直します。
普段から計算ミスに対して自分に厳しくしておきましょう。
「化学の新演習」の問題を全て解けるようになった時、大学受験の化学で怖いもの無しの状態になっています。
化学の新演習の次に行う問題集
「化学の新演習」を完成させることができたら、あとは過去問演習を行いましょう。
時間さえかければ問題は解けるという状態になっていると思うので、あとは過去問演習を通じて素早く正確に解く練習をしてください。
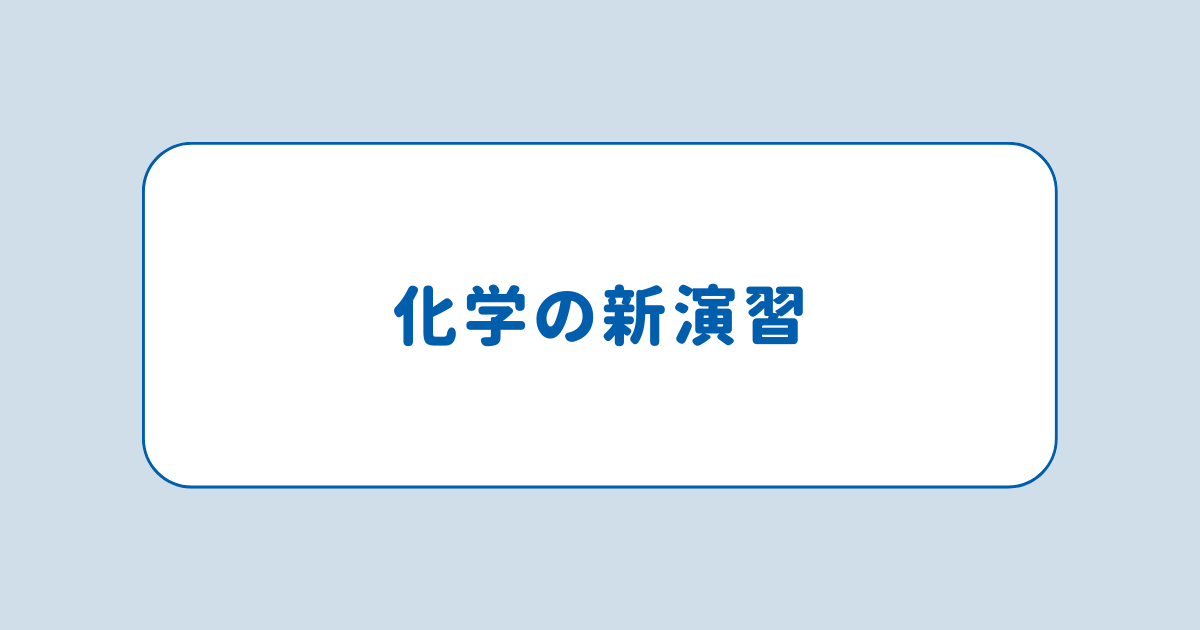
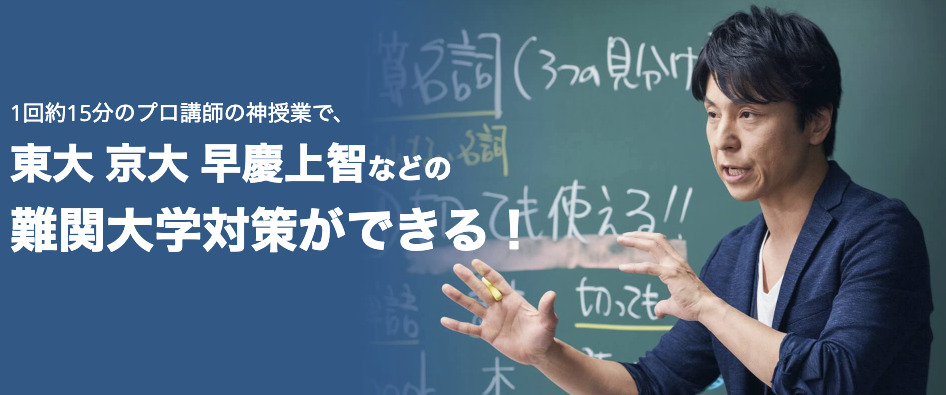


コメント